| ・・・・・・平成24年8月・・・・・・ | |||||||||||||
「貧者の一灯」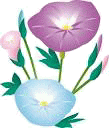 「長者《お金持ち》の万灯より、貧者の一灯」という言葉があります。これは『賢愚経』に示されている「もろもろの燈明(とうみょう)ことごとく滅したるも、ただこの燈のみひとり消えず」から生れた言葉と言われています。 『賢愚経』の「貧者(貧女)の物語」をお伝えします。 「長者《お金持ち》の万灯より、貧者の一灯」という言葉があります。これは『賢愚経』に示されている「もろもろの燈明(とうみょう)ことごとく滅したるも、ただこの燈のみひとり消えず」から生れた言葉と言われています。 『賢愚経』の「貧者(貧女)の物語」をお伝えします。昔、お釈迦様の時代に、一人の貧しい女がいました。名を難陀(なんだ)といいます。彼女は物乞いで、毎日食べ物を乞い歩いて生活していましたが、あるとき祇園(ぎおん)精舎でお釈迦様の説法があり、国王や大臣やお金持ちが、お釈迦さまやその弟子たちに灯明や品々を供養しているのを見ます。「私は貧しいが、みんなと同じように灯明を捧げて説教を聞くことはできないものだろうか」と思い、ある日、一日中歩いてようやく一銭を得ました。それを持って油屋に行き、「灯明の油を一銭分ください」と言うと、油屋は難陀に尋ねます。「一銭分の油では用が足りないだろう。いったいこれをどうするのか」と。すると難陀は「私は貧しくて、他の人の様にお釈迦さまにいろいろ供養することは出来ません。せめて、小さな灯明でも捧げようと思いまして・・・」。これを聞いた油屋はその心に感動し、油を二倍にして与えました。難陀は喜んで祇園精舎に行き、お釈迦さまに灯明を捧げながら、自分に向かってこう言います。 「こんな小さな灯明に、もしも功徳があるのなら、来世には明るい智慧を持って生れ、世の中の多くの人々の苦しみを取り除くことが出来ます様に・・・・」。こうつぶやいてその場を退きました。説法が終わり、夜中を過ぎ、他のすべての灯明は全部消えてしまったのに、この難陀の灯明だけ一灯が消えません。お釈迦様の弟子の目建連が三度も消そうとしましたが、ついに消えませんでした。お釈迦様はこう言います。「かの女人の美しい心は、仏の心と全く等しい。ゆえに大海の水をもってしても、永久に消えることはないのです」。 『真心の灯は、永久にともり続ける』、という教えです。この真心とは、「これだけしか供養できません。お許し下さい」と真から思う心も真心ですが、この『貧者の一灯』は違います。「この次に生れてきた時には、あらゆる人々の苦悩を救いたい」という真心です。この心を「大菩提心」と言い、お釈迦様の心と言うことです。自分の幸せよりも、すべての人を幸せにしたいという願いを起こし、その願いをもち続けることです。ひたすら人々の幸せのために捧げるのです。 「菩提心を発(おこ)すというは、己れ未だ度(わた)らざる前(さき)に一切衆生を度さんと発願(ほつがん)し営むなり」『修証義』 合掌
|
|||||||||||||
| 来月も予定しています。光泰九拝 |
|||||||||||||
ページ先頭へ |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||