|
「菩提の行願(ぼだいのぎょうがん)」
「若(も)し菩提心を発して後、六趣四生(ろくしゅししょう)に輪転(りんてん)すといえども、その輪転の因縁、みな菩提の行願となるなり。 然(しか)あれば従来の光陰は、たとい空く過ごすというとも、今生(こんじょう)の未だ過ぎざるあいだに急ぎて発願すべし。 たとい仏に成るべき功徳、熟して円満すべしというとも、なお廻(めぐ)らして衆生の成仏得道に回向するなり。 或いは無量劫(むりょうこう)行いて、衆生を先に度して自らは終に仏に成らず、但し衆生を度たし衆生を利益するもあり。」 (修証義・発願利生)
「若し菩提心を発して後、六趣四生に輪転すといえども、その輪転の因縁、みな菩提の行願となるなり。」
「六趣四生」の六趣は六道のこと。「六趣」の趣はそれぞれの業報によって趣き住む処という意味で、「四生」は、この世に生きとし生けるあらゆる生物をその生まれ方の上から、胎生・卵生・湿生・化生の四つに分類したもので、「四生」とはありとあらゆる生き物という意味です。
「輪転」は「輪廻転生」を二字に切り詰めたもので、人はあたかも車輪の廻転するが如く生と死を幾度となく繰り返し続けるという意味です。
この句は、「もし、菩提心を発こした後であれば、たとえ六道の何れの世界に生まれ変わろうとも、また四生の何れのものに生まれ変わろうとも、その者には衆生済度の誓願と実行が営まれるであろう。」ということです。つまり、菩薩道を行く者は、地獄道であろうが餓鬼道であろうと、どんな世界であろうとも衆生済度の誓願を携えている限り、その者は菩薩の立場にあるのです。
「自未得度先度他」を行願とする菩薩となったからには、たとえ地獄や餓鬼道へ往生しようとも、それは迷いの輪廻転生ではなく、衆生済度のための転生というべきものなのです。
「然あれば従来の光陰は、たとい空く過ごすというとも、今生の未だ過ぎざるあいだに、急ぎて発願すべし。」
「然あれば」というのは、「発菩提心には、以上述べてきたような深妙不可思議の大功徳があるのだから」という意味です。
「従来の光陰は、たとい空く過ごすというとも」とは、「これまでの人生のうち、欲望の虜となり、いたずらに空しい日々を過ごしてきたとしても、」という意味で、「今生の未だ過ぎざるあいだに、急ぎて発願すべし。」とは、「今の人生の命のあるあいだに急いで発心を決心しなければならない。」という意味です。
「たとい仏に成るべき功徳、熟して円満すべしというとも、なお廻(めぐ)らして衆生の成仏得道に回向するなり。」
「仏に成るべき功徳、熟して円満すべしというとも」というのは、「仏教の最高目的としての成仏の域に到達するために、それ相当の修行を重ね、功徳を積みあげてきて、その「功徳」が熟しきって、すぐにでも成仏できるその時に至ってもなお」という意味です。
「なお廻(めぐ)らして衆生の成仏得道に回向するなり。」 さらに己の成仏は後にまわして、衆生の成仏を先にするために己の「功徳」を衆生の方に振り向ける(回向)ことであるというのです。
「或いは無量劫(むりょうこう)行いて、衆生を先に度して自らは終に仏に成らず、但し衆生を度たし衆生を利益するもあり。」
「無量劫」の「劫」とは時間の単位ですが、千年とか万年とかいう程度のものではなく、計算仕様もないほどの遠大な時間のこと。「己以外の衆生を先に度(わた)らせて、己自身は迷える衆生が尽きない限り、永遠に成仏しない」。
「但し衆生を度たし衆生を利益するもあり。」但しは「ただひとすじ」という意味で、「衆生を度たし衆生を利益するもあり。」「度す」とは何度も言っているように「成仏」させることです。「利益」(りやく)とは利益(りえき)を与えるという意味ですが、精神的に安心立命させることです。ここでいうところの「利益は」とはお金が儲かるとか、病気が治るとかの浅はかな現世利益のこととは違い、真のご利益(ごりやく)とは、仏教の教えである仏法の智慧を身に付けることで、心身ともに「安心」(あんじん)することなのです。
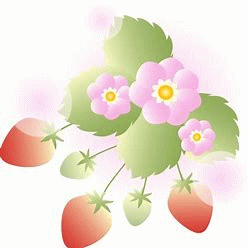 この「行願」とは、永劫に亘って、この世の一切衆生を最後の一人まで、ただひたすらに救わんとするものであり、その悲願が達成されないうちは決して己から成仏することはないとする、その「心」のことで、一切衆生をことごとく成仏させるまで永劫に六道輪廻をされているのが 「菩薩」であるという、この菩薩の「行願」の心こそ仏教の奥義なのです。 この「行願」とは、永劫に亘って、この世の一切衆生を最後の一人まで、ただひたすらに救わんとするものであり、その悲願が達成されないうちは決して己から成仏することはないとする、その「心」のことで、一切衆生をことごとく成仏させるまで永劫に六道輪廻をされているのが 「菩薩」であるという、この菩薩の「行願」の心こそ仏教の奥義なのです。
合掌
|
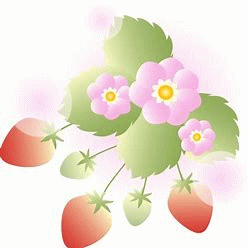 この「行願」とは、永劫に亘って、この世の一切衆生を最後の一人まで、ただひたすらに救わんとするものであり、その悲願が達成されないうちは決して己から成仏することはないとする、その「心」のことで、一切衆生をことごとく成仏させるまで永劫に六道輪廻をされているのが 「菩薩」であるという、この菩薩の「行願」の心こそ仏教の奥義なのです。
この「行願」とは、永劫に亘って、この世の一切衆生を最後の一人まで、ただひたすらに救わんとするものであり、その悲願が達成されないうちは決して己から成仏することはないとする、その「心」のことで、一切衆生をことごとく成仏させるまで永劫に六道輪廻をされているのが 「菩薩」であるという、この菩薩の「行願」の心こそ仏教の奥義なのです。