|
「菩提心(ぼだいしん)」
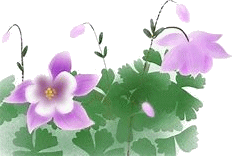
「どうしたら人は心の悩みや苦しみを無くすことができ、どうしたら心豊かな完成された人格を身に付けられるのか」の答えの一つを曹洞宗の教典・修証義の中の「発願利生」(ほつがんりしょう)が示しています。
「菩提心を発(おこ)すというは、己(おの)れ未(いま)だ度(わた)らざるさきに、一切衆生を度さんと発願し営むなり。
たとい在家にもあれ、たとい出家にもあれ、或は天上にもあれ、或は人間にもあれ、苦にありというとも楽にありというとも、早く自未得度先度他の心を発すべし。
たとい在家にもあれ、たとい出家にもあれ、或は天上にもあれ、或は人間にもあれ、苦にありというとも、楽にありというとも、早く自未得度先度他の心を発すべし。」(修証義第十八節)

「発願利生」の「利生」とは利益衆生(りやくしゅじょう)を切り詰めたもので、利益は利済(りさい)とか済度(さいど)という意味。つまり衆生を済度するということです。「衆生を済度する」とは、「人の為に尽くす」ということで、この心を「菩提心」といいます。自分のためよりも先ず他人のためを考える心のことです。人はふつう自分のことを先ず第一に考えます。自分にとって自分以上に大事なものはありません。自分こそ最も尊い存在なのですから、この感情は人として当たり前のものです。しかし、菩提心は違います。いつも自分のことより他人のことを心配しているのです。この心を起こすことを発菩提心(ほつぼだいしん)とか発心(ほっしん)と言います。
「菩提心を発(おこ)すというは、己れ未だ度らざるさきに、一切衆生を度さんと発願し営むなり」
菩提心を起こすこととは、自分のためよりも先ず他人のため、たとえ自分は彼岸に度らずとも、まず一切の他人を度さずには自分自身は決して度らないという利他の心こそ菩提心です。「済度」とは、迷いの「此の岸」から悟りの「彼の岸」へ衆生を「わたす」ということで、「わたす」とか「わたる」という場合には、「渡」という字を書くのが普通ですが、度も渡も同じ「わたす」という意味で使われます。「発願し営むなり」の「営む」とは、「実際に行ずる」という意味で、実行がなければ絵に描いた餅です。
「たとい在家にもあれ、たとい出家にもあれ、或は天上にもあれ、或は人間にもあれ、苦にありというとも、楽にありというとも、早く自未得度先度他の心を発すべし。」
この一段は前段の補足で、「たとい在家にもあれ、たとい出家にもあれ、」とは、在家、出家を問わずということであり、「或は天上にもあれ、或は人間にもあれ、」とは、天上界、人間界を問わずという意味です。「苦にありというとも、楽にありというとも、」とは、悪業の果報として、地獄界、餓鬼界というがごとき苦界に居ても、あるいは善業の果報を受け天上界という楽界に居てもという意味で、業の果報によって今現在如何なる身の上にあろうともということです。「早く自未得度先度他の心を発すべし。」 文字どおりに読み下せば、「少しでも早く、自らは未だ度ることを得ざる先に、他を度さんとする心を発するべきである」ということ。楽界に居る者はともかく、地獄・餓鬼・畜生・修羅・というが如き苦界の衆生が果たして「自未得度先度他の心」という律儀な心を起こすことができるのでしょうか。自己中心の我利我利亡者故にその業報により苦界に堕ちた輩に菩提心という高尚なものを期待すること自体所詮無理なことではないでしょうか。いやそうではありません。これこそ菩提心なのです。今現在、楽界にいる衆生は余裕があるからとか、苦界にいる衆生は余裕が無いからとかの問題ではなく、 楽界や苦界に居ることと菩提心を持つことに資格や差別はないのです。むしろ苦界にいる者こそ功徳は大きいとも言え、地獄・餓鬼・畜生・修羅などの悪趣の世界にこそ仏陀は救いの手を差し延べているのです。苦界に堕ちている者こそ救われなければなりません。その彼らが救われる道は只一つ彼ら自身が菩提心を持つことです。
「菩提心」は善人だけのものでなく、悪人には持つ資格はないなどというものでは決してありません。例え善人であれ悪人であれ、或いは裕福にあっても貧困にあっても、どんな境遇にあっても「菩提心」を持つことに一切の資格も制限もないのです。菩提心を持つことで苦界から救われるという、そこに仏陀は大慈悲心をもって復活の道を開いているのです。菩提心を持った者はみな「菩薩」となって自ら救われ、過去はどうであれ今ここで菩提心を持つことで誰でも「菩薩」になれるのです。我が身を顧みずにただただ苦境にある人達を救おうという一大決心をした人が即ち観音菩薩であり地蔵菩薩です。
合掌
|