|
「非風非幡(ひふうひばん)」
「無門関」の第二十九則「非風非幡」(ひふうひばん)を学びます。これは、動いているのは幡(はた)でも風でもなく、それを見ている人の心だという公案です。
本則
六祖、因(ちなみ)に風刹幡(せっぱん)をあぐ。
二僧有り対論す。
一(ひとり)は云く、幡動くと、一は云く、風動くと。
往復して曾(かっ)て未だ理に契(かな)わず。
祖云く、是れ風の動くにあらず、是れ幡の動くにあらず、仁者が心動くのみ。 二僧悚然(しょうぜん)たり。
「六祖」とは達磨大師を初祖としてその第六番目の祖師という意味で、大鑑慧能(だいかんえのう)禅師のことで、唐の時代、禅宗の黄金時代を築いた第一人者であり、まさに禅宗の中興の祖とも云うべきお方です。
刹幡(せっぱん)とは、寺で説法をする印に掲げる旗のことで、その幡を風が吹き上げていました。これを見ていた二人の若い僧が議論を始めました。
一人は「幡が動いている」と言い、もう一人は「イヤ風が動いているのだ」と言って互いに譲りません。その遣り取りを見かねた六祖は「幡が動くのでも、風が動くのでもない。お前さん方の心が動くのだ。」と言い放しました。その若い二人の坊さんは身震いしました。
以上が本則の内容ですが、常識から言えば風が動くから幡が動くのであり、それを己の心が動いているから幡も風も動くのだという、その真意とは一体何でしょう。結論を言ってしまえば、幡と風と心の実体が"一つのもの"だということです。しかしそれは机上の理論であり、机上の理論では答えにはなりません。以前から言っているように理論上の理解は絵に描いた餅です。本物を味わうには理論を超えた"実物"を会得するしかないのです。そのために必要なのが"証明"で、公案の意味合いはまさにここにこそあるのです。
公案はすべてそうですが、狙いは「三界唯一心」「心外無別法」という理論の"証明"です。宇宙の真理も仏法も、理論は単なる知識です。知識は分別です。分別は妄像ですから、その一切の分別妄想を断ち切るための証明が必要なのです。今回の公案で言えば、幡と風と心の実体は一如であるということの証明です。すなわちこの三者間にある一切の対立観念を完全に払拭するための証明です。
無門禅師は提唱しています。
拈提
無門曰く、是れ風の動くにあらず、是れ幡の動くにあらず、是れ心の動くにあらず、甚(なん)の処にか祖師を見ん。
若し者裏(しゃり)に向かって見得して親切ならば、方(まさ)に知る二僧鉄を買って金を得たり。
祖師忍俊(にんしゅん)不禁(ふきん)して、一場の漏逗(ろうとう)なることを。
六祖は「風が動くのではない、幡が動くのでもない。あなた方の心が動くのだ」と言われるが、かと言って、心が動くのでもない。無門禅師は「心が動くのでもない」と明言しているのです。六祖の言った「あなた方の心が動くのだ」という一言でその若い二僧が見性しさらに悟境を深めたら「心不動」という世界を徹底するだろう。そしたら、六祖の一言はその格下に見られるだろうということです。「六祖はつい口を滑らせたことで大きな失敗と恥をかいた」という表現はなにも六祖を批判しているのではなく、言貶意揚(ごんべんいよう)と言って口ではけなして心では褒めている禅門の特徴であり無門禅師の提唱では特に顕著です。その「心動かず」の真意とは何でしょうか。無門禅師は更に「頌」において提唱しています。
頌
風幡心動、一状領過す。
只口を開くことを知って、話堕(わだ)することを覚えず。
「風幡心が動く、などとは、二僧と六祖の三人は皆同罪である。ただ議論することは知ってはいるが言い損なったことに気が付いていない。」という意味です。「一状」とは、一通の判決状という意味で、三者の罪状は一通で間に合うという意味で、無門禅師は六祖をばっさり切り捨てていますが、その本意は六祖の悟境を讃えたものです。
「風・幡・心が動く」と「風・幡・心は動かず」との違いは、「心が動く」と「心動かず」に"差"があったら「事実」は見抜けないということです。「動く」が真に分かれば、同時に「動かず」が分かるのです。「動く」を観念として理解していたら絶対に分かりません。風・幡・心が真に不二一体のものならば、一体という認識も、不二という概念も、「動く」「動かない」という観念も、更に言えば「悟り」という観念もそこにはありません。あるのはただ「あるがまま」だけです。この世界には一切の分別はありませんから、無門禅師の言う「動くもの」など何もないのです。一切の対立観念もないから幡も風も心も無く「物我一如」なのです。
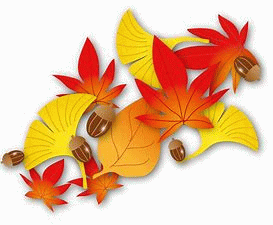
合掌
|